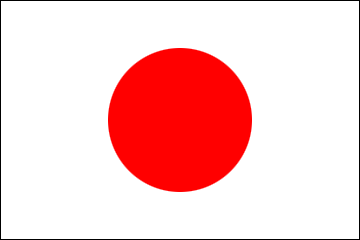大使挨拶 雲間からの光ーこの度の災害と皆様からの支援ー
令和4年1月24日
昨年の12月20日の朝、近くの島の火山が噴火したと現地職員たちが話しているのを聞いたのが始まりでした。トンガの首都のあるトンガタプ島から60数キロ離れたところにあるフンガ・トンガ島、フンガ・ハアパイ島という火山島で噴火が始まりました。数年前にも噴火した島であり、現地職員の会話にも特に深刻な雰囲気はありませんでした。海岸線から島は見えず、水平線から立ち上る、白い雲のようなものが見えるだけでしたが、その雲の中に頻繁に稲妻が走り、特に夜間の眺めは、不穏な気配を感じさせるのに十分でした。
12月末には火山活動も収まりつつあり、それまで噴煙の影響を懸念して運行が中止されていたNZからの週1便の貨物便(注;コロナが始まって以来、トンガに飛んでくる商業旅客便はありません。人が来られるのは不定期に運行される政府が認めた特別チャーター便のみ)も運行が開始され、令和4年、2022年の新年を迎えました。このHPにある私の新年の挨拶をご覧いただければ分かりますように、心配事はコロナ関連のみで火山のことは念頭にありませんでした。
1月14日(金)にこれまでより大きな噴火が観測され、津波警報も出され、午後からトンガ政府は閉庁となりました。現地のWeb新聞(Matangi Tonga)にその噴火の模様の写真が掲載されていますが、この時も我々に体感されるような音や揺れはなく、巨大な噴煙の写真も視点を変えればここまで接近しても問題のない火山活動だったことを示しています。12月の時のようにいずれまた収束するだろうと、思っていました。
1月15日(土)の午後5時過ぎ、休日で自宅で寛いでいた時にそれは始まりました。
これまで聞いたことのないような巨大な音、近くで大きな大砲を発射したような「バンッ」という音が空から響きわたりました。それに続いて、これも経験したことのないような衝撃が駆け抜けました。噴火の爆発による衝撃波だと今は言えますが、家や窓ガラスが撓むような激しい、音速で駆け抜ける衝撃、地面の揺れはない、地殻からではなく空からのもので、日本では経験したことのない衝撃でした。事態がよく呑み込めないうちに、同じような爆発音と衝撃が何度か続きました。空を見上げるとこれまでの噴煙とはけた違いの、海岸線ではなく内陸にある私の家からもはっきりと見える巨大なキノコ雲が空の半分を覆い隠していました。危機が今、目の前に迫っているのは誰の目にも明らかでした。
残念ながら今のトンガには、こうした時に機能する警報システムはありません。実は、こうした事態に対応するため、わが日本の援助による全国早期警報システム(NEWS)プロジェクトというものがあり、本来なら2020年の夏には完成する予定でしたが、コロナによる入国規制のため未完成だったことが悔やまれます。
ここではテレビ放送も極めて限定的で、直ちに臨時ニュースが流れるようなことはありません。国民が毎日親しんでいるラジオ放送が唯一の情報源でしたが、残念ながら全てトンガ語放送で我々には理解できません。現地職員経由で、ラジオで今、津波警報と高台避難が勧告されていると知ったのは、噴火後30分ほどもしたころでした。日本大使館は海に近いところにあるものの、トンガでは最も高い5階建てビルの5階にあるため、大使館職員は全員大使館に避難させました。
噴火が始まったのが土曜日の午後5時すぎで、市街地の人出もさほどではなかったこと、まだ日没前で明るかったことが不幸中の幸いでした。驚異的規模の噴火、そしてそれに続く津波にもかかわらず、在留邦人全員無事、全国でも死者が3名にとどまったのもこうした事情によるものと考えられています。
空からは激しい雨のように噴出物、火山灰が降ってきました。我々の島まで飛んできたのは、礫ではなく火山灰だけでしたが、見る間に辺り一面が真っ黒に染まっていきました。「月世界のようだ」と表現したのは、NZの外交官と仄聞していますが上手な情景描写だと思います。
噴火が始まって暫くはインターネットもつながっていましたが、6時半を過ぎるころには切れてしまいました。トンガのネット事情は悪く、こうしたことはしょっちゅう起きるので、暫くすれば復旧するのではないかとその時は思っていました。しかし、このシャットダウンは、噴火、津波によってトンガと世界をつなぐ唯一の命綱といっていい海底の光ファイバーケーブルが切断されたことによるものでした。その後はインターネットはもちろん国際電話も一切繋がらず、南海の孤島トンガでは、かくも火急の事態の最中、完全に世界から隔絶された日々が続くことになりました。
翌、日曜日の朝、我々が目にしたのは厚い火山灰で覆いつくされ真っ黒になった世界でした。海岸沿いの道路には無数の石、岩が散乱し、その中には打ち上げられたボートが混じっています。海と道路一本はさんで並んでいる家々のフェンスはなぎ倒され、庭に岩やボートが流れ込み家屋まで破壊されているところもありました。
トンガは敬虔なキリスト教国であり、安息日である日曜日は、教会と家庭内のこと以外は、仕事はもちろんレジャーも運動もしてはいけないと法令で決められています。店は全て閉まり、飛行機も船も動きません。土曜日に人や車でにぎわっていた繁華街もゴーストタウンのようになります。
しかし、さすがにこれほどの災害でしたので、政府は特別に午前8時から午後2時まで店を開くことを許可しました。今後のことを考えて買い物に行く車で道路の火山灰が巻き上げられ、砂吹雪のような視界の中で皆右往左往していました。
政府は、特に必要な業務に従事する者(エッセンシャルワーカー)を除き17日(月)は官民とも災害対応のための休日とし、翌火曜日から順次業務を再開していくとの方針を発表しました。大使館は特に事情のある現地職員を除き17日から全員勤務としましたが、最大の問題は通信情報システムがマヒ状態にあることでした。
大使館の場合、こうした事態に備え通信衛星を使った国際回線が確保できる機材を備えており、噴火直後からその運用を始めましたが島が噴煙で覆われている間はそれすらも繋がりませんでした。煙が晴れ、日本との国際電話は可能となりましたが一本の電話以外に通信手段はなく、またトンガの国内事情も現地語のラジオ以外は全く収集手段がありませんでした。トンガタプ島内では電話はつながっていたので、閣僚を始めとして各省庁とは頻繁にやりとりしましたが、彼らにしても現状については豪州やNZの飛行機からの観測情報ぐらいしか持ち合わせておらず、混乱というより混乱する以前の呆然自失の状態が続いていました。日本からの電話は我々の予想をはるかに超える緊急対応がわが国政府内で取りまとめられつつあることを伝えていました。
17日の夜には、外務省の特認を得て通信衛星経由でのインターネット接続が可能となりました。大使館の一室のみでの、しかも非常に遅い接続でした。
自分の顔を直接自分自身の目で見ることは物理的に不可能ですが、鏡あるいは写真を通して我々はいつも当然のように毎日自分の顔を見ています。15日の夕方から、ほんの2日間だけでしたが、完全に鏡のない世界で暮らした我々が、噴火ののち初めて接するWorld Wide Webの世界で見たものは…これまで見たこともない自分の顔でした…
***
ご挨拶と言いながら当時のレポートのようになってしまいましたが、ご覧いただけるような情報途絶の中、あくまで私個人が感じた当時の様子に過ぎず、正しいレポートができているとは思いません。ネットが通じてからは、限定的とはいえ日本の皆様とほぼ同じ状況認識、さらに日本国内の動きについては私共より日本の方々の方がお詳しいと思いますので、状況描写はここまでにしたいと存じます。
トンガは今もなお、世界でも限られたコロナフリーの国です。その代償として国は閉ざされ、令和3年の変異株発生によって入国はますます困難となりました。出国は比較的容易でも一旦出れば、次はいつ戻ってこられるか分からない状態では、責任ある大使館職員は出国できません。今の館員には2年以上にわたって、健康管理の休暇すらとれないまま医療が無いに等しいトンガで頑張っている者もいます。
私の新年挨拶にもあるように、その入国規制が緩和されるかと思われた矢先に、今回の災害となり、3人しかいない書記官の交代で24時間体制を続けています。ただ暗さはありません。むしろ日本をはじめとする各国からの暖かい言葉と迅速的確なご支援は、これまで余り陽の当たらなかったトンガに、火山の噴煙が晴れたとたん降りそそぐ明るい光のように感じております。
1月22日(土)の午後4時、わが国の航空自衛隊C-130が救援物資を積んでトンガのファアモツ国際空港に降りたちました。トンガの青空から、日の丸を背負った自衛隊機が舞い降りるさまは、それは感動的でありました。
日・トンガ外交史上初めての、この歴史的瞬間には、大使館、JICAの全日本人職員はもちろん、トンガの首相、副首相兼防災担当大臣、外務大臣、財務大臣、保健大臣、貿易・経済開発大臣らの多くの閣僚とトンガ国防軍司令官、大勢の政府高官が立ち会い、みんなで日の丸を振って歓迎いたしました。噴火直後から軍用機を運用している豪州、NZの近隣二か国を別にすれば、わが日本がトンガに救援物資を届けた初めての国となります。有難うございました。
切れた海底ケーブルは、復旧までまだ相当かかりそうですが、トンガ国内でも衛星を通じた海外とのコミュニケーション、インターネットへのアクセスが実現しつつあります。島はまだ火山灰に覆われ、特に津波の被害については殆ど手付かずの状況ではありますが、明るいトンガ人の気質と大家族の下での助け合いの精神で復旧に向かって進んでいます。まだまだ時間はかかるかと思いますが、皆様からのご支援を支えとし必ずや近い将来、良いご報告ができるものと確信しております。
重ねて御礼申し上げるとともに、今後とも引き続きのご支援を心よりお願い申し上げましてご挨拶とさせて頂きます。